JAFROSAX
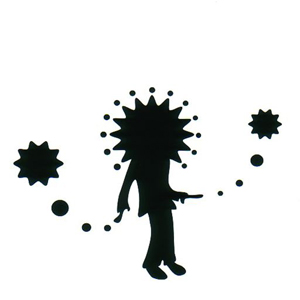
先にリリースされたアナログ盤がソールドアウトを記録するなど、正体不明のまま話題を呼んでいたユニット、JAFROSAXの全貌がようやく姿を現した。JAFROSAXとはサックス・プレイヤー、勝田一樹がクラブ・ミュージックに真正面から取り組んだプロジェクト。ファースト・アルバム『JAFROSAX』には国内外のトラックメイカーやシンガーがこぞってクレジットに名を連ねている。彼はこの新たなプロジェクトを発進させるきっかけを、「〈純粋な音楽的好奇心〉から」とする。
「クラブ・ミュージックにおけるトラックメイカーというのは、僕らジャズ・ミュージシャンからするとすごく斬新で、予想もつかないことをやっている感じがするんですよね。いったいどういう手順でやっているのかなって、そういうものを体験してみたいと思った。彼らと僕が合体したら、きっとおもしろいものが生まれるんじゃないかって」。
彼はみずから気になるアーティストに直電を敢行(!)。そして制作をスタートさせたのだが、当初はここまでヴォーカル・ナンバーがフィーチャーされる予定ではなかったという。
「JAFROSAXっていう名前にもあるように、当初はサックスをメインにした、インストのダンス・ミュージック的なものを考えていたんです。アクセントとして歌モノを入れる段階で、単なるJ-Pop的なものを作るつもりはなかったので、ヴォーカルをひとつの楽器として捉えてゲストの方に〈好きに歌ってください〉っていうスタンスでお願いしたんです。だから何も決めごとがなかったんですよ。ユキミ(・ナガノ)ちゃんみたいなメロウな感じのヴォーカルだったら、曲作りも柔らかくなりがちじゃないですか。でも今回はドンドンと4つ打ちのビートで歌ってもらって。それがミスマッチの妙で良かったなと思いますね。どうしても自分の知識のなかでやってしまいがちだから、別の感性を持っている人が新たな解釈をしてくれることで、ものすごく世界が拡がる」。
クラブ・ミュージックとジャズの融合──そうまとめてしまうのはたやすい。しかし、(もちろんすべてがそうであるわけではないが)カット・アンド・ペーストによりフィーリング重視の傾向に陥りがちな前者と旧来的な手法を重視する後者がここでは滑らかにミックスされている。しかもJAFROSAXのサウンドはいわゆる〈クラブ・ジャズ〉の文脈からもはみだしている。超絶技巧を駆使した、彼いわく〈人力〉のサックス・プレイヤーとしてのプレイヤヴィリティーと同時に、いちリスナーとして無邪気に音と戯れてもいる。なにより多彩なトラックの上で縦横無尽に暴れまわる彼のサックスは、実に闊達で楽しそうだ。
「すごく刺激的ですよね、○○風とかではなく、その道のスペシャリストが作るトラックの上で吹くことは。僕も自分の演奏スタイルを変えたほうがいいのかなと思ったんですけれど、ありのままを、やり過ぎっていうくらいまで押し通してしまいました。もちろんサックス・プレイヤーとしてのJAFROSAXというのは前に出る名前だと思うんですけれど、全体のトラックをトリートメントしていく、全体の印象をイメージ付けるにはどうしたらいいかというのは随分考えましたね。だからプレイヤーとしてはもちろん、より客観的に自分の作品を聴かなきゃいけない立場でした」。
そうした彼のプロデューサーとしての卓越した仕事ぶりは、今作の完成度を聴いていただければ説明するまでもないだろう。彼自身、「まさかここまでポップになるとは思っていなかった」というこのアルバムの仕上がりには満足しているようだ。
「ポップな楽曲にジャジーなエッセンスが入るサウンドって、ありそうでそんなになかった。ジャズ・ミュージシャンでここまでポップなトラックを作れる人はいませんよ(笑)」。
PROFILE
JAFROSAX
66年生まれ、神奈川出身のサックス・プレイヤーである勝田一樹によるソロ・プロジェクト。88年よりスタジオ・ミュージシャンとしてプロ活動を始めた彼は、92年に増崎孝司、小野塚晃らとジャズ/フュージョン・ユニット、DIMENSIONを結成し、多数のオリジナル・アルバムをリリースする。2003年よりJAFROSAXを始動させ、ユキミ・ナガノやLISAをフィーチャーしたファースト・シングル“Going to the sky”をリリース。セカンド・シングル“Rollin'”には、NOKKO、ヴィクター・デュプレが参加して話題となる。このたび、福富幸宏、野崎良太(Jazztronik)、GAGLEらが参加したファースト・アルバム『JAFROSAX』(コナミ)をリリースしたばかり。


